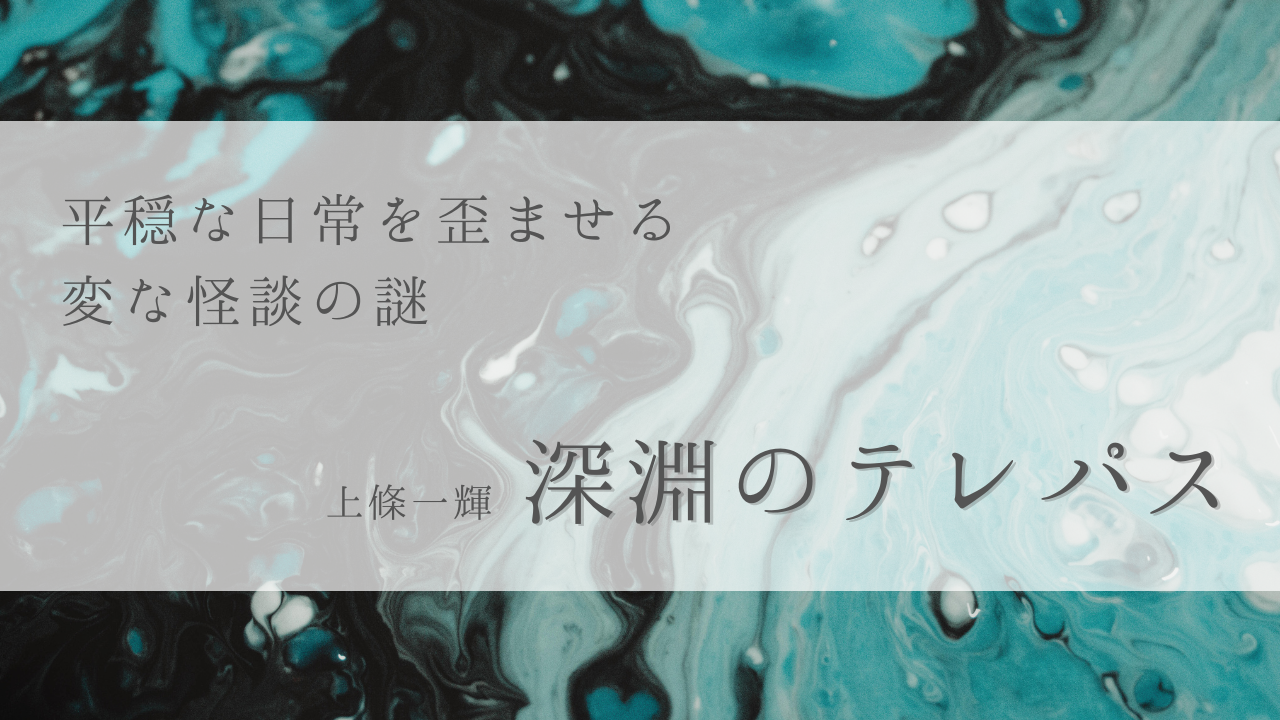この本について
書誌情報
| タイトル | 深淵のテレパス |
| 著者 | 上條一輝 |
| 出版社 | 東京創元社 |
| 発売日 | 2024年8月16日 |
| ページ数 | 256 |
あらすじ
「変な怪談を聞きに行きませんか?」会社の部下に誘われた大学のオカルト研究会のイベントで、とある怪談を聞いた日を境に高山カレンの日常は怪現象に蝕まれることとなる。暗闇から響く湿り気のある異音、ドブ川のような異臭、足跡の形をした汚水――あの時聞いた”変な怪談”をなぞるかのような現象に追い詰められたカレンは、藁にもすがる思いで「あしや超常現象調査」の二人組に助けを求めるが……選考委員絶賛、創元ホラー長編賞受賞作。
感想
何よりもエンターテインメント性の高さが魅力
Xの読了ポストをきっかけに知った本です。Xで目にしなければ存在に気付くことはなかったと思われます。というのも、ホラーが苦手なのでホラー小説の類に対するアンテナをほぼ立てていないからです。
これはホラーというよりもミステリーでは?とあり、それならいけるかも!とAmazonページに飛んだところ、『創元ホラー長編賞受賞作』『このホラーがすごい!』『ベストホラー2024』『今読むべきホラー』などとホラーの字が躍りまくっていて、怯みました。ホラーの許容レベルは人によって全く違うので、こういう時に自分はいけるかどうかの判断が難しいですよね…。ちなみに私はホラーを避け続けてきた人生だったために、どこまでならいけるのかすらよくわかりません。初代『かまいたちの夜』のピンポンピンポン鳴るシーンは未だに怖いです。あれはホラーではないか。
とにかく、無理そうなら途中で断念しようと決めて読み進めることにしました。結果的には、全く問題なし。上記のピンポンの方が100倍怖いです。作中で起きるホラー現象としてはあらすじにあるものが大部分で、実際の被害に遭っているカレンの視点による描写も多くはなく、読んでいるこちらにまで迫ってきそうな恐怖感はありませんでした。個人的にはホラー耐性がそこまで高くない方でも読める感じはしますが…、判断はお任せします。逆に恐怖のどん底に突き落とされるようなホラーを期待して読むと拍子抜けしそうです。
ミステリーについては、確かにそういう要素も含まれていましたが、全体を通してミステリー小説と言えるものではないと思います。ジャンルとしてはやはりホラー小説と言うのが妥当でしょう。
まとめると、ミステリー要素もあるホラー小説でホラーレベルは低め、です。ただ、この小説の魅力はホラーやミステリーにではなく、エンターテインメント性の高さにあると私は思っています。あらすじの通り、怪談を聞いてからカレンの身の回りで怪現象が起きるようになり、調査を依頼された「あしや超常現象調査」の二人が中心となって怪現象を起こさせない方法を探っていく流れで、その退屈させない展開のテンポ感が終盤まで気持ち良く続きました。話も説得力があり、わかりやすくまとまっています。ホラーやミステリー、そしてスリルをつまみ食いしながら楽しめる話を求めているなら、この本をおすすめします。
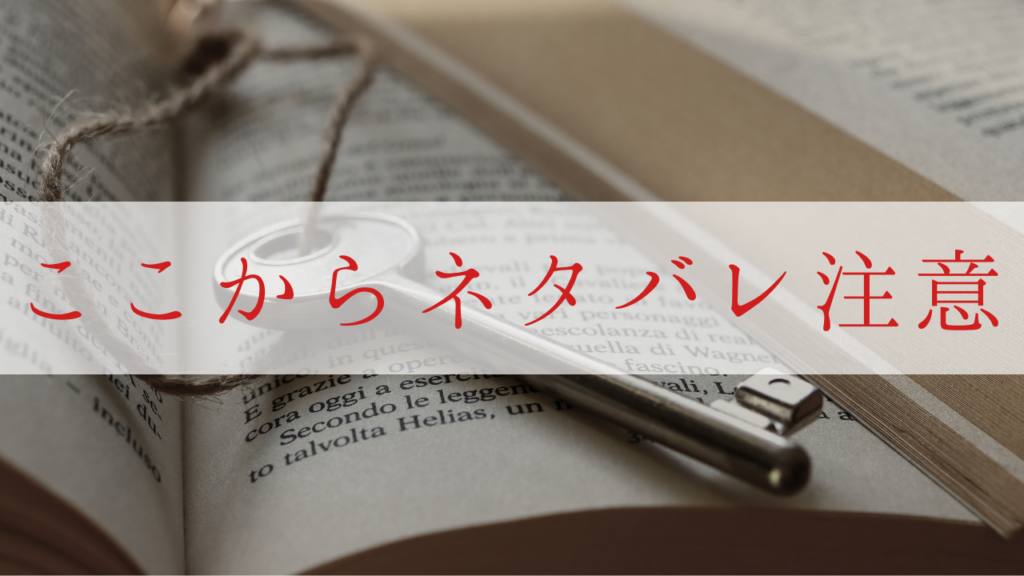
【ネタバレあり】引っ掛かった部分を挙げるなら…
先に書いた通り退屈させない展開で面白かったのですが、最後の洞窟が崩れて閉じ込められたところからは流石にご都合主義を感じました。戦時中のオカルト研究所はフィクションといえど潰しておくべきだろうけれどタイミングがすごいなとか、越野に活躍をさせるなら晴子は邪魔だろうけれど鉄筋を貫通させるのは中々だし、そこから越野の助けに入らせるのも中々の無茶だなとか。その辺りを差し引いても楽しめたのは間違いありません。
ご都合主義といえば、探偵倉元の使える手が強過ぎるというのもありました。土曜日に登記簿を取るなんて芸当、相手が結構な立場の人間だとしても相当難しい気がしますが。…ご都合主義の話を考え出すとキリがなくなる上につまらなくなってしまうのでこの辺りでやめます。どうしても引っ掛かった部分ということで。
まとめ
感想を書いていて改めて思ったのは、まとまりが良過ぎるがゆえに長く記憶に残るものではないかもしれないということでした。筆致が淡々としているせいか、やはりホラー小説にも関わらず恐怖心をそこまで煽る内容ではないせいか、面白さの割にはインパクトに欠けてしまっている印象です。この雰囲気でガチガチのホラーを書いてみてほしいと思ったものの、そういえば私はホラーレベルが上がってしまうと読めなくなるのでした。残念。
既に続編の『ポルターガイストの囚人』が発売されています。メインで活躍する登場人物4人のことは好きになれたので、そちらもぜひ読みたいと思います。なんなら桐山も今回で出番が終わってしまうには惜しいと思えるくらいには好きでした。シリーズ作品らしく晴子の過去について匂わせられていたので、いつかその開示編も来るかもしれないと考えると楽しみですね。
最後に本筋とは関係ないのですが、心に残った文章がありました。出勤シーンの描写です。
一様に黒いスーツに黒い髪の、色味のない男女が、天井の低い地下道を肩をすぼめて行進していく。僕もその葬列の一部だ。葬られるのは、夜までの一日の時間であり、六十五歳までの四十年の人生だ。
上條一輝『深淵のテレパス』p.37
地下道を出て、銀座の北側の垢抜けないエリアに向かう間も、葬列は続いている。みなそれぞれの職場という名の棺桶に吸い込まれて消えていく。
強く共感できてしまったせいかもしれませんが、ここは一番気持ちが入っているように感じられまして。これが作者のリアルな声だとするなら、パワハラのくだりはリアルな話でなければ良いなと思ったのでした。