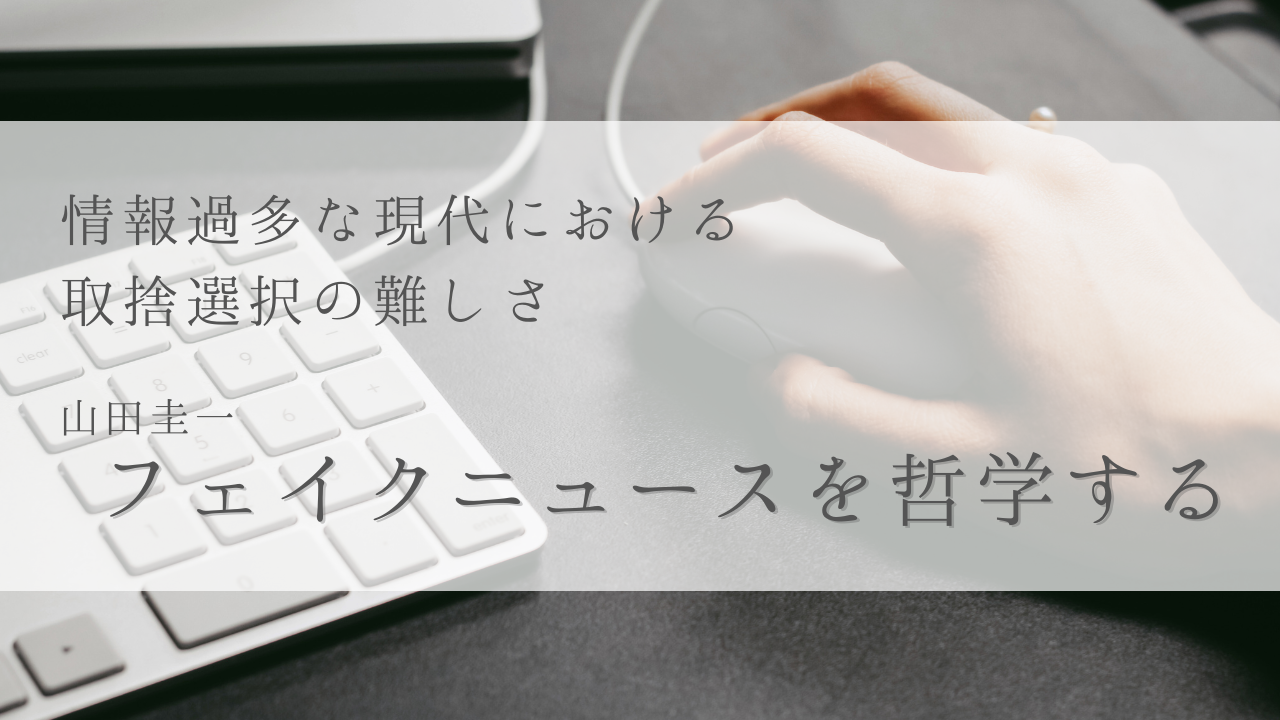この本について
書誌情報
| タイトル | フェイクニュースを哲学する──何を信じるべきか |
| 著者 | 山田圭一 |
| 出版社 | 岩波書店 |
| 発売日 | 2024年9月24日 |
| ページ数 | 206 |
あらすじ
他人の言葉、うわさ、専門家の発言、マスメディアの報じるニュース、ネット発のニュース、あるいは陰謀論……、私たちは瞬時に莫大な情報を手にする一方、時に何を信じたらいいのか、わからなくなってしまう。本書では、「知る」ことを哲学的に考察し、「真理を多く、誤りを少なく」知るための方法、そしてその意味を問う。
章立ては下記の通り。
序章 フェイクニュースとは何か
第1章 他人の言っていることを信じてもよいのか
第2章 うわさは信じてよいものか
第3章 どの専門家を信じればよいのか
第4章 マスメディアはネットよりも信じられるのか
第5章 陰謀論を信じてはいけないのか
終章 真偽への関心は失われていくのか
感想
情報社会で何を信じるべきかという問い
フェイクニュースとは、「「情報内容の真実性が欠如しており(偽であるか、ミスリードである)、かつ、情報を正直に伝えようとする意図が欠如している(欺くことを意図しているか、でたらめである)」ものとしてひとまず定義することができる。(p.5)」とありました。ただしこれ以外にも様々な観点があって、本の中では厳密に定義を決めずに捉えることとしています。
フェイクニュースという言葉は、いつの間にか一般化していたイメージがあります。あまり気にしていなかったのに、ふと周りを見渡せばみんなが使っていた感じで、広まり方が早かったからこそ人によって定義がバラついているのではないかと思います。それ以前に、定義を気にせず使っている人の方が多いかもしれませんね。先の定義は、個人的には納得感があります。
この本は、大量の情報が流れ込んでくる現代で一体何を信じるべきなのか、その基準はどこにあるのかといった問いについて、フェイクニュースや陰謀論などの話題に触れながら考えていくものです。
「哲学する」というタイトルの通り話が哲学的な方面から進んでいくので、大きな流れとしてはわかりやすくても、細かい部分で難しさを感じるところはありました。「認識論」や「仮説推論」といった言葉がまず難しいです。ただ、読み進められないほどの難しさではないので、あまり心配はいらないと思います。
インターネットは世界中の情報に、瞬時にかつ低コストでアクセスすることを可能にしてくれた。このことがわれわれの知識の獲得にもたらした恩恵は計り知れないが、他方でインターネットによってわれわれと知識との関係が大きく歪められている側面もある。その最たる例がフェイクニュースの蔓延であり、科学否定論や陰謀論などの浸透である。
山田圭一『フェイクニュースを哲学する』p.iii
真理への関心を失うとはどういうことか
特に怖いなと思ったのは、フェイクニュースの広がりによって生じる問題点として挙げられていた、「人々が真理への関心を失っていく」ことです。著者によると、その事態は既に進行しているとのことでした。
進行しているとしても、今はまだ真理への関心を持つ人が多数派からこそ、フェイクニュースや陰謀論はある程度のところで食い止められているのではないかと私は思います。真理への関心を持つ人が少数派になれば、楽しかったり面白かったりすれば良い、自分さえ注目を浴びられれば良いといった発想が一般的なものになり、例えばSNSはでたらめな情報が飛び交う無法地帯になるのでしょうか。私は単純に、それは正しくないと感じるので嫌です。本の中では真理の価値の話などについても述べられています。
第3章は専門家がテーマです。真理への関心がなくなれば、専門家の意見も不要になりそうです。今はまだ専門家の意見も重要と思われていて、だからこそ自称専門家、フェイクな専門家といった存在が現れているのでしょう。これも怖い話です。
フェイクな専門家がさまざまなフェイクな学説をネット上で流布していたとしても、既存の専門家はそれに気づくこともないし、たとえ気づいたとしても多くの専門家は反論する必要性すら感じないだろう。(中略)しかし、このような交わることのないフィールドの外側でフェイクな学説が徐々に信奉者を増やし続けていることは、既存の知的権威の土台が静かに掘り崩される事態を招いている。
山田圭一『フェイクニュースを哲学する』p.115
まさにそういう事例があったような…?と思い出したのが、『土偶を読む』(2021年)です。在野の研究者が書いた考古学の本なのですが、専門家が問題点を指摘しても売れ続け、子供向けの本まで出版されたため、『土偶を読むを読む』という検証本が出版されるに至ったという話です。(『土偶を読むを読む』という書籍を出します。|note)
更に思い出したのが、ゲームの歴史の解説本『ゲームの歴史』(2022年)です。出版直後から読者だけではなく業界関係者からも事実と異なる内容を様々に指摘されて炎上し、最終的には販売が中止される事態となりました。
この2冊が辿った道筋の違いは、対象となった分野における有識者の数や層の違いによるものかと思いましたが、それに加えて真理への関心度合いの違いもあったのかもしれません。私は先の真理への関心を失っていく話について、あらゆるものの真理に対して一律に関心を失っていくことを想定していました。もしかすると実際にはそうではなくて、こちらの分野における真理への関心は保ちつつも、あちらの分野における真理への関心はなくしてしまうというように、対象ごとにその関心度合いが異なるのではないかと思ったのです。
『ゲームの歴史』は持論のために事実が捻じ曲げられている、真理ではないと批判されていました。『土偶を読む』も専門家から同じ批判をされていたのに、「「そうは言っても、こういうものを否定したら、自由な発想が出なくなってしまうじゃないか」、「縄文時代は答えがないのだから何を言ってもいいじゃないか」とは、僕も何度か言われている。」(上記noteから引用)とのことで、真理より面白さを重視する読者も多そうに見えます。
『ゲームの歴史』を批判した人は真理への関心を失っておらず、『土偶を読む』を評価する人は真理への関心を失っているという形で、この両派が完全に分かれた人種であるとは思えません。なので、対象ごとに関心度合いが違うように感じたのでした。実際に私自身も、よく知らない分野に関するところでは真理への関心を持たず、「まあ面白ければ良いんじゃない?」なんて軽く言ってしまう可能性もないとは言えません。
難しいのは、真理への関心は絶対に持たなければならないのか?ということです。ものによっては関心がなければないで良いとも思うのですが、ただ失ってはならない場面があるとも思うというか…。自分の中で整理できていないので、今後も考えてみます。
まとめ
正直なところ、フェイクニュースや陰謀論といった類のものは思っている以上に身近に存在しているのでしょうが、自分がそれを信じ込んでしまう事態は想像できません。仮に信じたとしても、私はあまりリポストという行動を取りませんし、人間関係も限られているので現実世界でデマを広めるリスクも低いと思われます。…なんて油断していると良くないわけですね。
フェイクニュースや陰謀論を信じてしまうのは必ずしも本人の資質のせいではなく、その資質にしても、相手の意見や批判をきちんと聞けるという良い特性を持っているからこそ陰謀論者の主張を受け入れてしまう場合もあると述べられていました。
私自身としては、そうしたものの発信者にならないことは当然として、安易なリポストなどで真偽不明の情報を拡散しないように、信じたくなる情報も一度立ち止まって吟味するように、そんな態度を保っていきたいと思えた1冊でした。