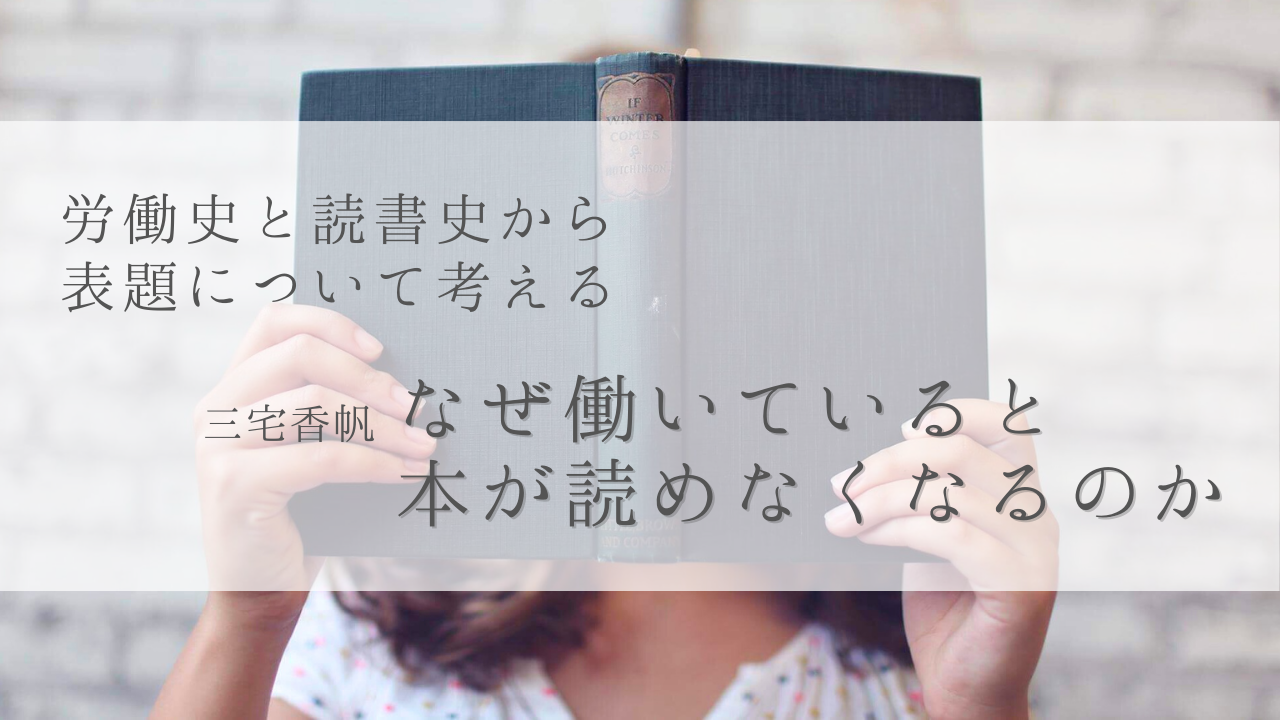この本について
書誌情報
| タイトル | なぜ働いていると本が読めなくなるのか |
| 著者 | 三宅香帆 |
| 出版社 | 集英社 |
| 発売日 | 2024年4月17日 |
| ページ数 | 288 |
あらすじ
【人類の永遠の悩みに挑む!】
「大人になってから、読書を楽しめなくなった」「仕事に追われて、趣味が楽しめない」「疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう」……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
「仕事と趣味が両立できない」という苦しみは、いかにして生まれたのか。
自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。
そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?
すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。
章立ては下記の通り。
まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました
序章 労働と読書は両立しない?
第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生―明治時代
第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級―大正時代
第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?―昭和戦前・戦中
第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー―1950~60年代
第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン―1970年代
第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー―1980年代
第七章 行動と経済の時代への転換点―1990年代
第八章 仕事がアイデンティティになる社会―2000年代
第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?―2010年代
最終章 「全身全霊」をやめませんか
あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします
感想
労働史と読書史から見る日本人の本
話題になっているのは知っていて読みたいと思いつつも、中々手に取れずここまで引っ張ってしまいました。…と思ったら、まだ発売から1年経った程度でした。このタイトルをあまりにも目にするので、既に2年は経っているものかと。
それにしても、本を読む人間としてはとても気になってしまうタイトルです。「確かに、なぜなんだろう!」とつい前のめりになります。このタイトルというか問題設定が時代に合っていたからこそよく売れたのだろうなと思っています。
ところで私は、本が読めなくなる一番の原因は、スマホを中心とする手軽な娯楽の方に時間を奪われているからだとなんとなく考えていました。なので、この本も脳科学的な話題が多いのではないかと勝手に思っていたのですが、的外れでしたね。
紹介文を読めば明らかな通り、労働史と読書史を並べて、日本人の労働と読書がどのような関係を結んできたのかを時代順に見ていき、そこから本を読めないと感じる理由を探ろうという流れになっています。日本人の労働に対する考え方の変遷や、ビジネス書が求められる時代背景の話題など、なるほどなあと面白く読みました。
「新しい文脈をつくる余裕がない」
結論は第九章と最終章にあります。端的に言ってしまうと、本が読めないのは、自分に必要のない情報(ノイズ)を取り入れる余裕がないからとのこと。
自分から遠く離れた文脈に触れること―それが読書なのである。
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』p.234
そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係のあるものばかりを求めてしまう。それは、余裕のなさゆえである。だから私たちは、働いていると、本が読めない。
この文脈やノイズといったくだりは、忙しくて時間が足りず、それで読書をはじめとする趣味の時間が取れていないはずなのにスマホゲームはできてしまう、そんな状況をビシッと言語化されているので少し感動しました。確かに自分の感じていたもやもやを言語化するとこうなるな、と。
私の場合、実は働いていても本は案外読めています。なぜかと言うと、昼休憩の時間で読書しているからです。休憩が1時間あり、30分で食事と歯磨きなどを済ませて、残りの30分は読書という形。休日はだらだらすることも多いので、むしろ平日の方が読めている時もあります。
とはいえ、そこで読む本はシリーズ作品だったり偏ったジャンルだったり、あるいは軽く読めるものだったり。骨太の長編作品や普段読まないジャンルなどは選ばれません。これも、「新しい文脈をつくる余裕がない」ことを理由に挙げられそうです。
ちなみに関係ない話ですが、私が休憩時間に読書しているのに影響されたと言って、同じく休憩時間に読書をするようになった上司がいました。あれは嬉しかったです。何を読んでいるのか聞けなかったのが心残り。
あとがきでは、著者の考える働きながら本を読むためのコツが紹介されています。個人的にはいまいちピンときませんでしたが、3番の習慣にするという部分には納得です。上記の昼休憩の話もまさに習慣にできていたわけですし。自分に合いそうなものがあれば試してみるのも良いと思います。
まとめ
「新しい文脈をつくる余裕がない」のが問題ならその余裕があれば良いわけですが、その余裕をつくるのがまたとてつもなく難しいというのは、世の中の大半の人が共有できる意見でしょう。最終章では、全身全霊で働くことを求める社会や全身全霊のコミットメントを楽だと感じる人間の話が紹介され、それでも全身全霊をやめるべきという著者の主張が展開されます。全身全霊ではなく半身で働くことができれば、もう半身分の余裕が生まれるというのです(半身社会)。
その半身社会をどう実現するかの具体案はなく、この本にそこまで求めるものでもないだろうとは私も思いますし、皆で望めば叶うかもしれない、そういう社会にしていきたいとして締めるのは、1冊の本として綺麗でした。綺麗でしたが、正直なところ夢物語が過ぎるとも感じてしまいました。もちろんそうなってほしい気持ちしかありませんが…。
そういえば、第九章では新自由主義の話もありました。新自由主義思想を持つ人とは、要するに自己決定や自己責任の論理を内面化している人のことで、例えばひと昔前なら社会のルールを疑っていたところを、自分の責任ではないかと感じるわけです。
私は先に、「本が読めなくなる一番の原因は、スマホを中心とする手軽な娯楽の方に時間を奪われているから」と考えたと書きました。責任の所在を自分にしているので、もしかしたらこれも新自由主義的な発想から来ているのかもしれません。…なんて、自分の思考の根について考えられたのも面白かったです。
この新自由主義に染まった半身社会などあり得るのだろうかと、また話が戻ってしまうのですが。とにかくまずは半身社会の賛同者が増えるところからだと思うので、ぜひこの本を読んで半身を提唱していきましょう。
AI時代における、人間らしい働き方。
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』p.20
それは、「労働」と「文化」を両立させる働き方ではないでしょうか。