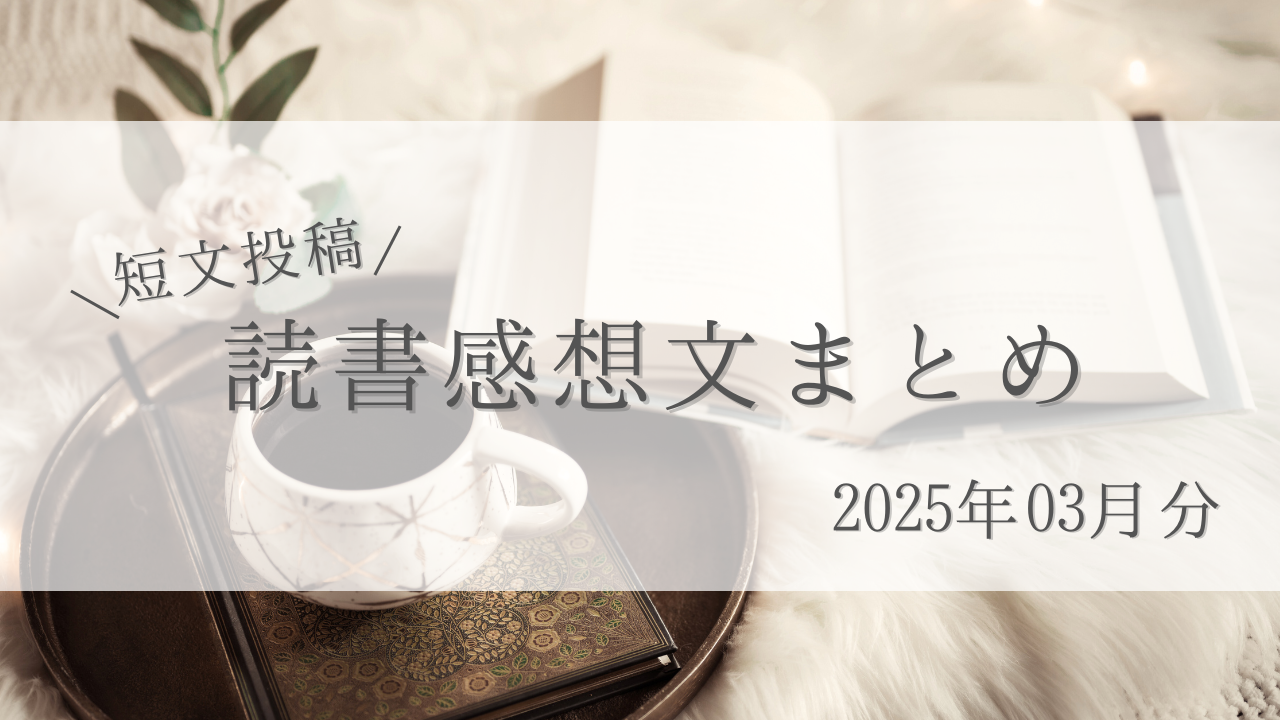投稿した感想とあらすじ
Xに投稿した読書感想文をまとめました。
アカウントはこちら。https://x.com/momoji_212
暇と退屈の倫理学
#哲学
「暇」とは何か。人間はいつから「退屈」しているのだろうか。答えに辿り着けない人生の問いと対峙するとき、哲学は大きな助けとなる。著者の導きでスピノザ、ルソー、ニーチェ、ハイデッガーなど先人たちの叡智を読み解けば、知の樹海で思索する喜びを発見するだろう──現代の消費社会において気晴らしと退屈が抱える問題点を鋭く指摘したベストセラー、あとがきを加えて待望の文庫化。
哲学書を読むのは初めてなので理解できるか不安だったが、
わかりやすさと面白さを見事に兼ね備えた本だったので、
まんまと他の哲学書も読む気持ちになっている。
経済学や生物学などなど、幅広い分野からアプローチされていたのが良かったなあ。
https://x.com/momoji_212/status/1897284488331452747
濱地健三郎の呪える事件簿
#ミステリー #短編
JR新宿南口に「濱地探偵事務所」はある。年齢不詳でダンディ、美術品への造詣が深い探偵は、幽霊を視る能力を持っている。幼いころ漫画家になりたかったという助手の志摩ユリエは、その絵心を生かして、心霊探偵が視たモノを絵に描きとめるのも大切な仕事だ。ここには、奇妙な現象に悩まされる依頼人だけでなく、警視庁捜査一課の辣腕警部も秘密裡に足を運び、濱地の推理を頼みにしているのだ。
リモート飲み会で現れた、他の人には視えない「小さな手」の正体。廃屋で手招きする「頭と手首のない霊」の姿に隠された真実。濱地と助手のコンビが、コロナ禍で一変した日常に潜む怪異と6つの驚くべき謎を解き明かしていく。
ホラー苦手な私でも楽しめる怪異シリーズの3作目。
この世界でもコロナかぁ…と思ったが、
そうした状況下だからこその怪異というのも確かに面白い。
友情話でもありつつ、巡り合わせの恐怖も語られた『伝達』が好き。
https://x.com/momoji_212/status/1901242964938256467
中国不動産バブル
#新書
中国の不動産バブル崩壊が幕を開けた。
それは貨幣的な現象に留まらず、金融、行政、政治システムへと飛び火し、やがては共産党統治体制をひっくり返す要因にもなり得る――。
バブル形成から崩壊まで、複雑怪奇な構造をどこよりも分かりやすく読み解く。
不動産市場の実情だけではなく、政治や経済分野まで幅広く解説されている。
共産党指導体制の下で様々なものが影響し合っているのがよくわかった。
そもそも発表される統計が信用できないのだから経済対策も難しいとのことで。
– – – – –
著者によるとバブルは既に崩壊しているそうだが、となると今後もその影響が気になる。
ちなみにこの本が発行されたのは2024年4月。
https://x.com/momoji_212/status/1903438994681307187
たべるたのしみ
#エッセイ #食べ物
“私にとって食べることは、生きることだ”
永遠に輝き続けるおいしい味の記憶を綴った54の物語。
文筆家・甲斐みのりが、これまでに書籍・雑誌・新聞等に寄稿した食にまつわる膨大な随筆から54篇を厳選し、大幅加筆して再構成した待望の随筆集です。誰もの心の奥にある、いつのかの日の食の記憶を思い出し、懐かしい人や風景が鮮明に呼び起こされます。「たべるたのしみ」が存分に味わえる、あたたかく美味しい随筆集です。(※改訂前の紹介文)
食べ物エッセイ。
幼い頃の記憶が綴られた話も多いせいか、どこかノスタルジックな雰囲気。
美味しくて幸せな思い出をたくさん覚えておられるのだなと羨ましくなった。
一部を除き見開き2ページ程度の話が続くので、さらさらと読める。
– – – – –
池波正太郎さんの随筆をよく読んだという下りで紹介されたお菓子「好事福盧」。
坂木司さんもどこかのエッセイで触れていた記憶がある。
私も池波先生よろしく窓の外で冷やして食べたい!と思って…早何年かしら…。
https://x.com/momoji_212/status/1905257004228280784
(私が読んだのは改訂前の版)