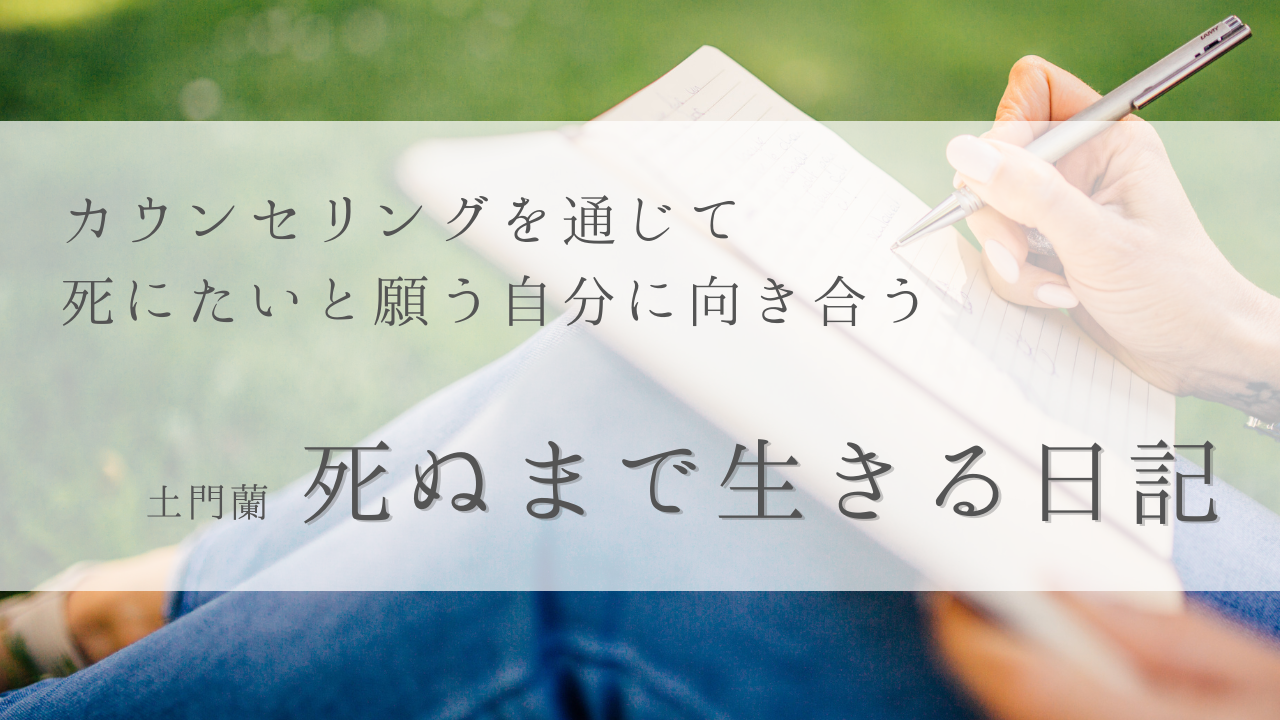この本について
書誌情報
| タイトル | 死ぬまで生きる日記 |
| 著者 | 土門蘭 |
| 出版社 | 生きのびるブックス |
| 発売日 | 2023年4月20日 |
| ページ数 | 264 |
あらすじ
10歳の頃から「死にたい」と願う気持ちを抱えて生きてきた著者の土門さん。なぜそういう願いを持つに至って、それが今まで続いているのか、そしてできればその願いが消えないかと、カウンセリングを受けることに。カウンセラーの本田さんと対話しながら自分と向き合い続けた2年間の記録本。
章立ては下記の通り。
第1章 私は火星からやってきたスパイなのかもしれない
第2章 「『死にたい』と感じてもいいのだと、自分を許してあげてください」
第3章 「自分で自分の『お母さん』になれたらいいですね」
第4章 「肯定も否定もせずに、ただ感情に寄り添ってみてください」
第5章 「『解決しよう』と思わなければ、問題は問題ではなくなるんです」
第6章 「私はずっと、日本人になりたかったんです」
第7章 「『過去』は変えられなくても、捉え直すことはできます」
第8章 「あなたは、必死に生きようとしています」
第9章 地球以外の場所で、ひとりぼっちでものを書く人たち
第10章 居心地の良いように「火星」を作り替えていけばいい
第11章 「生きている限り、人と人は必ず何かしらの形で別れます」
第12章 「書いて、読むことで、私たちは何度でも出会えます」
最終章 「お守り」を感じながら生きていく
感想
希死念慮がある側としての感想文
「本当にみんな『死にたい』と思わないのですか」
土門蘭『死ぬまで生きる日記』p.19-20
思い切ってそう尋ねると、
「思いません」
医師はやっぱり、あっさりと否定した。
この本はカウンセリングの記録を綴った本ですが、土門さんはその前に医療機関を受診されています。上記はその一場面です。
最初に言っておくと、私は「死にたい」と願う気持ち、いわゆる希死念慮がある側の人間です。なので、本の内容のあらゆる箇所に共感ポイントがありました。(土門さんほどの希死念慮ではなく、日常生活には支障ありません。)
そんな私にとって、「普通は死にたいと思わないのか?」というのは長年の疑問でした。中々身近な人にできる質問ではありませんし。そして引用した通り、医師に「思いません」と答えられているのには驚きました。死にたいと思わない人生が想像できないのです。そのためこの答えに対して疑う気持ちが正直拭い去れないわけですが、本当に死にたいと思ったことのない人にとっては当然の答えなのでしょう。
このように、希死念慮のない人からすると考え方が真逆の感想を書いている可能性もあります。その辺りはそういうものかと流してもらえれば幸いです。
とりわけ共感したポイント2選
共感したポイントを挙げてみます。
目の前で起こるさまざまな変化に対して、その都度感情は湧き起こるのだけど、根っこの部分がずっとうつろだ。何かに夢中になったとしても、その感情はすぐに冷えて、うつろな気持ちに引き戻される。そしてそのことを、夢中になっている最中にも予感している。
土門蘭『死ぬまで生きる日記』p.16
共感ポイントその1。「うつろな気持ち」、わかります。この本の終盤には、芥川龍之介の遺書に記された「唯ぼんやりした不安」という言葉が出てきて、土門さんは自分の気持ちにしっくりくると話していました。私も強く同意します。
とはいえ私はどちらかと言うと、「根っこの部分がずっと不安」なのかもしれません。それは中身のない不安なので、うつろと言えばうつろですが。心か頭の片隅でいつも実体のない不安を感じていて、目の前の楽しいことに100%集中できていない気がします。
「『死にたい』と言うと、周りの人は自分が否定されたような気持ちになるんじゃないかなと思うんです。一緒にいるのにどうしてって。周りの人を傷つけるのではないか、迷惑をかけるのではないか、失礼に当たるのではないかと思って、言えません」
土門蘭『死ぬまで生きる日記』p.39
共感ポイントその2。全く同じ理由で言えません。本の中で、カウンセラーという離れた立場の人にだからこそ言えるといった話が何度か出てきていましたが、その通りだと思います。身近な人であるほど、自分の本心に近いことは言いづらいです。厄介ですね。
たまに小中高生の自殺のニュースが流れてきます。その時、なぜ相談しなかったのかという声が上がりがちですが、そう簡単に言えることではないと思います。思春期なら尚更です。周りの大人はなぜ気付かなかったのかという声についても、隠している側から言うと、見破るのは相当難しいと思います。明白な身体症状が出るならまだしも…。死にたいと思ったことがないからこそ言える意見なのかもしれませんね。
こんな調子で共感ポイントが色々と見つかった結果、土門さんがカウンセリングを受けた記録を読みながら、私もカウンセリングを受けているような気分を味わえました。それに、そう感じているのは私だけじゃなかったのかと思えただけでも勇気付けられます。
例の本を通じて見えた自分との違い
読み進めていくと、土門さんは死にたいと思いながらも自分が強くならなければと努力を続け、今も必死に生きようとされていることがわかります。死を恐怖している節もあります。
先に共感したと色々書き立てましたが、この根本的なところは私と違うなと思いました。私は死をそこまで恐怖していないからです。(多分)
途中で、『完全自殺マニュアル』という本の名前が出ていました。土門さんは一線を越えることを恐れて、絶対に手に取らなかったと話しています。私は中学生か高校生の頃にその本の存在を知った気がします。興味はあったものの、家族に見つかったらまずいなと思って買えませんでした。
聞くところによると、この『完全自殺マニュアル』は自殺を推奨する目的で書かれたものではありません。いざという時はこの本の通りにすれば死ねるという安心感を頼りに生きていこうと、生きづらさを感じる人が生きるための本なのだそうです。
恐らく土門さんのような人は、この本を持っていても安心感には繋がらないでしょう。私は、その安心感は持っておきたいかもなと思います。ここが違います。そういう意味で、私は希死念慮があると言いながらも気楽な調子でいられるのかもしれません。あまり健全ではないのですが…。
まとめ
自然な死が訪れるまで、死なずに生き続けること。
土門蘭『死ぬまで生きる日記』p.9
(中略)そうしたいと願っているすべての人に、この本を捧げたいと思う。もしも、ほんの少しでも誰かの「死ぬまで生きる」ための力の支えになれば、これほど嬉しいことはない。
ページが進むにつれてカウンセリングの回数も増え、土門さんの前向きな変化が読者にもよく伝わってきます。テーマがテーマなので、読み始める前は気持ちを引きずられることがないかと少々不安もあったのですが、読み終えた後にはなんとも言えない満足感がありました。
カウンセリングの過程や結末について、ここではほぼ触れませんでした。ぜひ自分の目で読んで確かめてみてほしいです。認知行動療法やマザーリングといった、困っている人の支えになりそうな手法の話もありました。
それから本文とは別に、各章末で土門さんが落ち込んだり辛くなったりした時に助けられたという本の紹介がありました。この紹介文がまたそそられる内容で、私は読みたい本リストに何冊も入れました。思い返すと、私も以前死にたい気持ちが強くなった時に、何かしら助けになる本はないかと図書館をぐるぐる見て回ったものです。その手の探し物をしている人にもおすすめです。