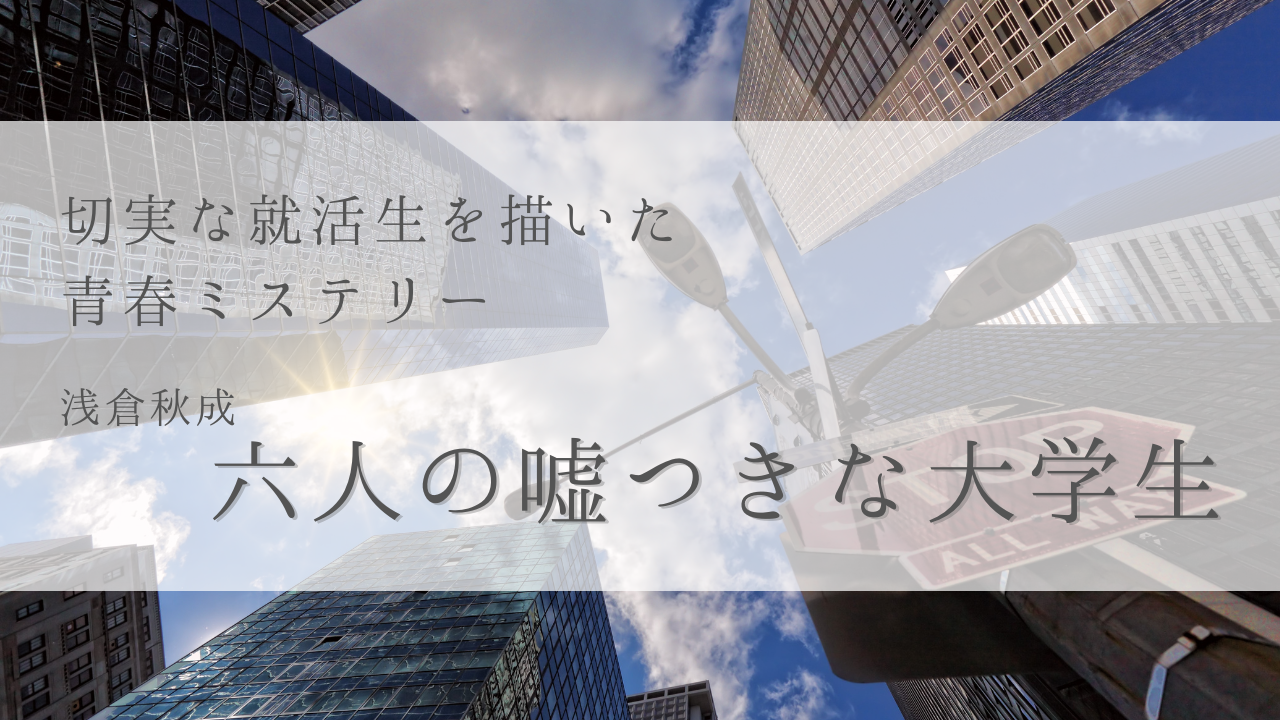この本について
書誌情報
| タイトル | 六人の嘘つきな大学生(角川文庫) |
| 著者 | 浅倉秋成 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2023年6月13日 |
| ページ数 | 368 |
あらすじ
成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用。最終選考に残った六人の就活生に与えられた課題は、一カ月後までにチームを作り上げ、ディスカッションをするというものだった。全員で内定を得るため、波多野祥吾は五人の学生と交流を深めていくが、本番直前に課題の変更が通達される。それは、「六人の中から一人の内定者を決める」こと。仲間だったはずの六人は、ひとつの席を奪い合うライバルになった。内定を賭けた議論が進む中、六通の封筒が発見される。個人名が書かれた封筒を空けると「●●は人殺し」だという告発文が入っていた。彼ら六人の嘘と罪とは。そして「犯人」の目的とは――。
感想
青春小説として面白い作品
単行本出版の頃から話題になっていたのを耳にしてはいましたが、中々機会が持てず、文庫化してから読むことになりました。
文庫本の帯には『圧倒的共感&衝撃のどんでん返しミステリ!』とあります。
どんでん返しという宣伝法はいかがなものかという問題はさておき、この煽り文や、裏表紙あらすじの人殺しという文言を見て、「表面上は良い人を演じていた大学生たちが、告発文を契機に豹変し、嘘と裏切りに塗れたドロドロの令和版バトルロワイアル的な展開になるのかしら」と勝手に想像していた私。
結論を言ってしまうと、そんなレベルの過激さはありません。正直少し残念でした。
共感の部分は理解できました。新卒採用の選考に挑む学生側の気持ちは、経験者はもちろんですが、仮に経験していなくてもわかるのではないかと思います。
個人的には、ミステリー小説として面白いかと言われると頷きかねる部分があります。
なんの前情報もなければまた別だったかもしれませんが、煽り文などを見て、自分の中のハードルをかなり高くしてしまったことが原因だと思います…。ただ、ミステリー要素のある青春小説として面白いと言われれば大いに賛同します。
就活生という、ある意味では夢の中に生きているような危うい存在の6人が、それぞれに切実な思いを抱えながら幸福や絶望を味わう様には、心を揺さぶられました。
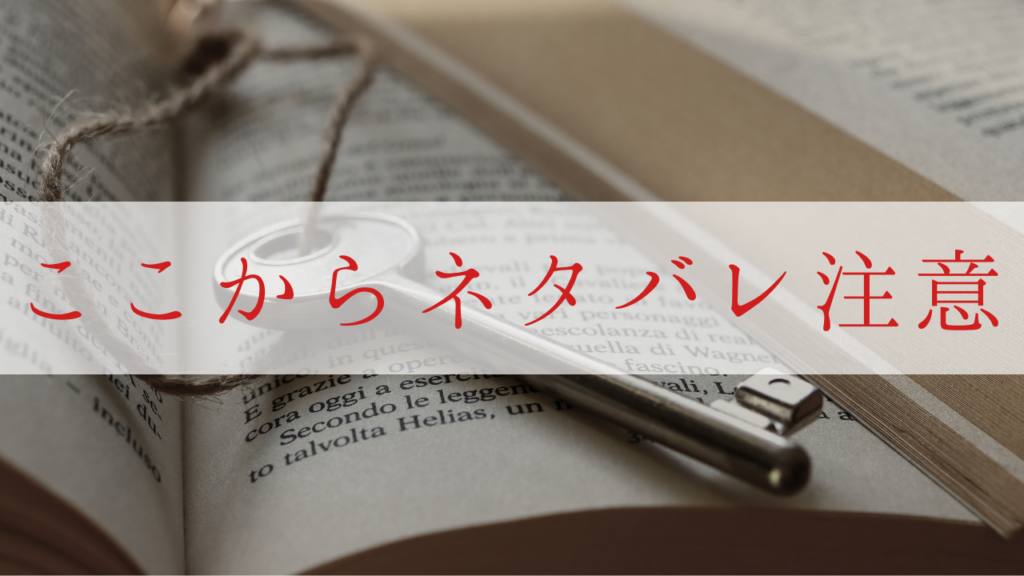
【ネタバレあり】改めて全体を見てみると
ネタバレなしの部分で、「ミステリー小説として面白いかと言われると頷きかねる」と書きました。
まず、話の進行に合わせて情報が開示されるという点があります。読者が推理することは困難です。犯人をほぼ確定させることのできるタイミングは、嶌と同じ245ページ辺りです。
飲み会の途中で九賀が波多野を誘って中座するシーンは、私の感覚ではあまりにも不自然でした。ミステリーと言われれば、語り手が信頼できるかどうかにも注意を払う性質なので、敢えて語られないタイミングは注目してしまいます。あそこはもう少し自然に馴染ませてほしかったというのは、私のわがままです。
動機という面でもいまひとつです。確かに友達の話は出てきていましたが、そこから想像できるわけがないと違う意味で驚きました。動機などというものは十人十色で、自分に理解できないものがあっても当然だとは思いますが、それにしてもメリット皆無でそこまでするのかと。
真相を話す場面での九賀は、メンバーの汚い過去が出るわ出るわで、波多野も飲酒以上のとんでもない非道を働いていて、嶌も含めてろくでもない人間たちだったと語っているわけですが、恐らく嘘です。どういう気持ちでそんな話をしていたのかよくわかりません。自身の行為の正当化でしょうか。
そもそもの選考方法が変なので、私はそこを疑っていました。九賀も犯人だが、更に…という展開です。どんでん返しの煽り文もあったので、まだ返しがあるのかではと。それはなかったですね。なかったからこそ、鴻上はおかしいという思いを強くしました。これは後述します。
インタビューの描写とラストでそれを引っくり返すところは、上手いと思いました。ただ、犯人当てに関係する部分ではないので、ミステリー部分への評価には繋がりませんでした。
ミステリー以外のところで言うと、一番良かったなあと思ったのは、波多野がしっかり生きていたということです。自分を犯人扱いされるという酷い体験をして、留年して日本最大手の会社に就職して、病気になっても働きづめで、結局亡くなってしまって。しかも好きな女性を犯人だと思い込んだままだとしたら…と、暗澹たる気持ちでいたのですが、遺されたファイルを読むと落ち込んだままの人生ではなかったとわかって、安心できました。
そういえば、波多野が嶌を犯人だと思い込んでいたという部分にも騙されました。騙されたというか、ここであの不自然な中座シーンが関係してくるわけですが。
それから、鴻上に送らなかった手紙が出てきたのも良かったです。これがなければ、波多野が完全にただの良い奴で終わるところでした。もちろんただの良い奴でも構わないのですが、こういう腹黒部分があるからこそ人間らしくて愛せるなと感じてしまいます。嶌も同じような気持ちになったからこそ、「好きだったよ」と言えたのではないでしょうか。悲しいかな、337ページを見るに、当時の嶌は波多野ではなく九賀に気があったようなので。
【ネタバレあり】個人的な●●批判
先にも書いた通り、選考方法が変なのでそこに疑いを持っていたわけですが、288ページからの鴻上インタビューを読んで驚きました。まさか単なる思いつきでこんな手段を取ったとは。
学生同士で選んで一人を決定して、しかしながらその一人が内定者になるとは限らない、議論の内容を見て判断する、というのならまだわかります。それを、学生同士で選んだ一人を内定者にするなんて。しかも、告発文が発見された後でディスカッションを中断させるべきではないかと訴えた部員がいたにも関わらず、続行するという判断。鴻上は何を考えているのかと思いました。
彼を嫌いになった決定打は、61ページの「今となっては笑い話ですけどね。」の一言。これは、選考そのものを指しているのか、選考によって役員に叱られたことを指しているのか、はっきりしません。
しかしいずれにしても、当事者となった6人が言うのならともかく、生殺与奪の権を握りながらモニターを通して見ていることしかしなかった担当者がそれを言うのかと。それも当事者だった嶌の前で。6人に同情を寄せるあまり過剰に反応している節もありますが、それでも無神経だと思いました。
就活生の人生が左右されるイベントとは言っても、担当者にとっては仕事の一つに過ぎないのでしょう。その範囲内の話であれば、あまり強くは言えません。ただ、鴻上は仕事をしたと言えるのでしょうか?
相手の本質を見抜くことは不可能であるという考えはわかります。それでも責任を持って選んで採用するのが仕事だったはずです。彼は最終選考の6人までは選んだのかもしれませんが、最後の一人を選ぶ仕事を、いわば放棄しています。それでいて59ページで、「自分が採用に携わった社員というのは、少なからず自分の「子供」のような愛着が芽生えるものですよ。」なんて言い出すのだから呆れます。
これ以上続けると悪口が止まらなくなるので終わります。怒りの感情は筆が乗りますね。
【ネタバレあり】まとめ
全体を通してのテーマは、人は見えている一面が全てではないということだったと思います。
私も鴻上の悪口を書きましたが、他の面を見ればもしかしてもしかすると印象が変わるのかもしれません。
もう一つ言いたいのは、全体的に採用に対するイメージが少し古いと思ったことです。作中の出来事はコロナ禍以前に起きているので、その頃から考えても古いのかどうかはわかりませんが。
九賀は就活システムを大批判していました。鴻上は人事の内情を吐露していました。
どちらの話も一面では真実だと思いますが、採用の前提がとにかく優秀な人物を選び出すという点に置かれていたことが気になりました。もちろん優秀であればそれに越したことはないと思いますが、採用はそれだけの要素で決まるわけではないと考えます。例えば、会社、社風との相性もそうです。九賀の友達のようにいくら優秀な人物であったとしても、この会社には合わないと判断されて落とされる可能性はあります。(今回は偶然九賀と鴻上の考えが一致しているのでその限りではなかったようですが。)
少しズレた例かもしれませんが、コロナ禍以降で実際に聞いた話です。ある中小企業に、応募者のボリューム層とは違う、高学歴で優秀と思われる人物からの応募がありました。採用できるのならば採用したい、とりあえず次のステップには進めたいと思ったそうです。しかし、結論としてその人物は落とされることになりました。なぜかと言うと、第一志望ではない確率が高いと考えられたからです。その人物に内定を出して断られるくらいなら、最初から落として他の人物に席を譲った方が良いという思い切った判断でした。
鴻上の言う運の要素もあると思います。要するに、完全無欠の超人であっても、上から下まであらゆる会社の内定を得るのはほぼ不可能だということです。
今の私の感覚からすると、そういう考えになります。今回は九賀と鴻上の考えが一致しているので、彼らの感覚が一般的な世界なのだろうとは思いつつ、ズレを感じてしまったところでした。
そして私の感覚で言えば、九賀の動機は青いと思いました。就活システムにおいても、限られた面しか見えていなかったのではないかと。波多野の遺した言葉を、嶌が伝えてくれていると良いなと思います。
※2024年11月22日に実写映画が公開されました。